
「窟観音 2」の続き。朱塗りのお堂の一番手前の千体仏。
願掛け千体仏で、必ず参拝者と目が合う仏様があると言われる。

2つ目は弘法大師を祀る岩屋。弘法大師像と聖観世音菩薩の2体が安置され、どちらも大師自作の石仏とされている。

3つ目(この写真では一番手前)が、窟観音本殿。本尊の聖観世音菩薩像と十王尊(地獄の裁判官)、心鏡が安置されている。

本殿から下る石段の途中から見上げる。まさに断崖雪壁と言える岩山に半分以上飲み込まれたような異世界的な眺めだ。

石段を下まで降りてもう一度見上げる。弘法大師は、よくこんなところにお堂を開く気になったものだと感心する。
次回に続く。

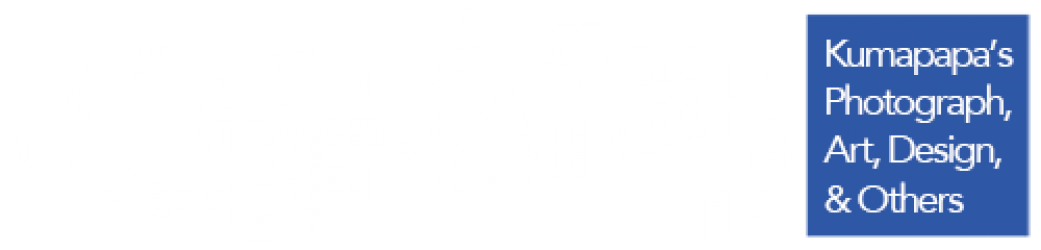
こんにちは。
スゴいところに造ったものですね。
当時の技術でどうやって造ったのでしょう?
気になりますね。
くまごろーさん、いらっしゃい。
全く感心してしまいますね。
最初は平安時代のことで、断崖の途中にある天然の洞窟に弘法大師が石仏を安置したことから始まったそうです。
建物が作られたのは江戸時代だそうで、その後も何回か改築や修復が行われて維持されているとのことです。